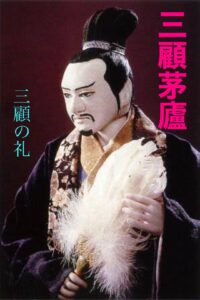玄徳公の祥月命日に寄せて

成都留学時代は玄徳公に精神的に助けられ
支えられた玄子(げんし)です。
今日は旧暦4月24日。
劉備(玄徳)公が崩御された祥月命日です。

日本語では歴史上の人物に敬称をつけないのが
「正しい」日本語と言われているようですが、
私は大好きな三国志の英雄たちに対しては、
日本語の正しさよりも礼儀の正しさを大事にしたいので、
玄徳公、とお呼びします。
玄徳公以外の三国志の英雄に対しても同じ。
孔明先生、曹操閣下って風に敬称を略さずに
敬意を剥き出しにしていきますので予めご理解ください。
この時点で違和感のある方は、さよ〜なら〜(^^)/~~~
また、今日は1記事1万文字に挑戦します。
ぎゃ〜長い文章は嫌じゃああ!って方も今のうちにお逃げくだされ!
今更ですがこのブログは三国志の流れや登場人物を一通りご存知の方向けです。
登場人物ごとに丁寧な説明や読み方は補足しませんので、重ねてご了承ください。
では、参りまする!
目次
玄徳公と三国志
私は三国演義を通してこの世界(ってどの世界( ̄∀ ̄)?)に入りました。
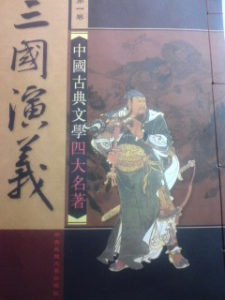
最初に三国志の世界に案内をしてくれた英雄は玄徳公でした。
横山三国志も、NHKの人形劇三国志も最初は玄徳公が注目を浴びます。
きっと、登場したときの玄徳公は
まだ無名の一般庶民だったから
親しみを覚え易かったのかも知れません。
これが張飛殿、関羽殿だったら武力とか髭の長さとか
既にもう違うわ〜って客観的に見てしまうので、
魅入ることはなかったかも。
三国志の流れを知った後で関羽殿を主役にした物語とかなら
「待ってました!」って最初からテンション上がるかと思いますが、
三国志の世界に入る、
最初の最初の第一歩はやっぱり玄徳公だからこそ、
人々の共感と応援を得たのかも知れません。

それがきっと、三国志の主役と呼ばれる所以の一つ。
そんな玄徳公の魅力を即席で列挙してみます。
あくまでも私が感じる魅力ですので反対意見や反論は一切受け付けませぬ〜。
個人の自由で玄徳公への思いの丈を綴るだけですので宜しくご理解ください。
大きな耳と腕
まずは玄徳公の外貌。
耳たぶを自分でも確認することができるほど
大きかったというのは、陳寿が証言しています。
仏像の大きな耳をイメージする感じでしょうか?

史書に書かれるくらいだから、
第一印象に残るほどだったのではないかと思われます。
さらには、膝まで伸びる長い腕だったと
陳寿は証言を続けています。
そんな特徴的な外貌と、
玄徳公の人間力って実はすっごい密接していたのです。

↑成都にいる玄徳公。
話すのが苦手でも英雄たちが魅了されたわけ
玄徳公は喜怒哀楽の情を顔に出さない、
寡黙な人だったことでも知られています。
これも陳寿からの垂れ込み情報です。
寡黙、とは口数が少ない人のこと。
玄徳公におかれましては、口数だけではなく、
文字数も少なかったとか。
相手が長文のお手紙を出しても
「元気だよ、ありがとう!」だけで返信するタイプ。
説明したり、思っていることを言葉にするのが
面倒って感じていたのかも知れません(^◇^;)
その代わり、前半は関羽殿が、
後半は孔明先生が玄徳公の言いたいこと、
伝えたいことを汲んで
上手く説明してくれていたので、
話すのが苦手でも問題なし!
なので「話すのが苦手だから友達が少ない」は言い訳にはならないのです。
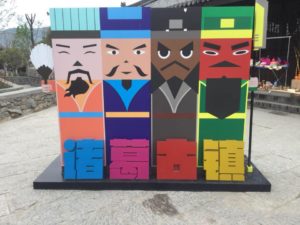
素晴らしい仲間に支えられた、寡黙な玄徳公。
話すのが苦手なのになぜ、天下に名だたる英雄を
仲間にできたのか?といえば
聞き上手だったから!!!
玄徳公に学ぶ聞き上手の極意
聞き上手とは相手にただ話をさせるだけではありません。
相手の言いたいことを引き出す聞き方をしているのです。
その分かりやすい例が、
玄徳公とその御子息にして後主となった劉禅の違い。
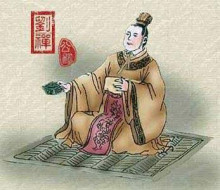
玄徳公は、それはそれは真剣に、
一言も聞き逃すまいと臣下の話に耳を傾け、
いいと思ったら積極的に意見を取り入れていました。
なので諸将は「玄徳様〜!私の意見も聞いてください!!!」
競うように献策をしていました。
ただでさえ、目立ちがり屋が多いであろう三国志の時代(笑)
数多いるライバルを抑えて
目立ちまくるには、
国にとってより良い意見を
積極的に主張する必要があった!はず。
その意見を心いくまでガッツリ聞いてくれて、
尚且つ基本口数の少ない玄徳公がコメントをしてくれるとなったら、、、
そりゃもう、国のため、玄徳様のためって忠義を尽くさずにはいられなくなったのです。

その際たるものが20歳も年下の孔明先生に
天下三分の計を熱弁させたことではないでしょうか?
そんな玄徳公の血を受け継ぎながら、、、どうしたことでしょう?
劉禅陛下は、
「そんな難しいこと言われても知らないしぃ〜。
どうせ僕はパパ(玄徳公)には及ばないよ」
自分を卑下し「どうせ」を口癖のように言っては、
臣下の話を真剣に聞こうとしませんでした。
家臣の皆さん的には
玄徳公のような対応を求めていました。
というか、それこそが
蜀の勢力が魏や呉に比べて弱かったにも関わらず、
堂々と渡り合えた理由の一つでもありました。

話を聞くのは嫌いだけど、おしゃべりは好き。
世間話とか政治に関係のない話には簡単に応じていたとか。
玄徳公と対照的な劉禅陛下。
ある程度、国が強くなって余裕ができたなら、
それでも構わないけど、まだまだ危急存亡の秋(とき)。
「まずは真剣に、しっかりと臣下の意見に耳を傾けてください。
分からないことがあればその都度、聞けばいいのです」
とアドバイスしていたのが

孔明先生でした。
話すのが苦手、を理由に
人付き合いを諦めてしまわぬよう、
話すのが苦手なら聞き役として
玄徳公のような皇帝レベルを目指すのもありです!
玄徳公の耳は、臣下や民衆の声をしっかり聴くように
大きかったのではないでしょうか?
天下を包み込む腕
次に膝まで届く腕!
私の場合、膝まで届くのは丁度、自分の手をもう一個分加えた長さでした。
玄徳公の凄いところは、
孔明先生を迎えるまで各地を転々としていて、
居城の一つも持てずに客将だったこと。
それなのに!名門や豪族、豪傑が次々と滅んでいく中、生き残る強さ。
人間、肩書きや生まれた環境、
学校での成績よりも大切なことが
人生において最も大事なことだと玄徳公の生き方に学べます。

それが腕の長さと何の関係が?って話ですが、要は器の大きさ。
玄徳公の腕の長さって
イメージ的にこんな感じだったんじゃないでしょうか?

なんかよく分からないけど
「この人に賭けてみよう」とか
「下手に手出ししたら、なんかヤバいんじゃない?」って思わせる人間力。
身長は決して高くない玄徳殿が、
長身の関羽殿、張飛殿、孔明先生と並んでも
引けを取らなかったのは
彼らさえ包み込んでいると思わせる
腕の長さがあればこそ。
いうまでもなく、ただ腕が長いだけではありません。
前述したように目の前の相手を大事にする、
話をしっかり相手目線で聞く、
そして大きな腕を広げて受け止めるー。
そんな玄徳公だからこそ、
腕の長さを存分に生かして
他の人には届かない皇帝の地位を
手に入れることができたのではないでしょうか?
これは特に根拠はなく、私の個人的な見解です♪
過大評価しすぎ?
そんなことはありません。私にとって玄徳公はそれくらい大きな存在。
ってことで誰も興味ないだろうけど、
私と玄徳公の時空を超えた奇跡を告白します( ̄∀ ̄)
玄徳公と三国志と私
私が最初に玄徳公率いる三国志の英雄たちに助けられたのは中学の時でした。
当時十三歳だった私は「読書」という有り触れた趣味以外、
これと言って好きなことも特になく、特技は本当に何もなく、
成績も見た目もパッとしない!
それなのに、いじめの標的にされて無駄に目立っていました。
生きることも、死ぬことも許されない日々は、
天地人、だけではなく神さえも敵となっては
「みんな仲良く」「命を大切に」といった詭弁の刃を私の首筋に当てるだけで、
具体的な救助策も解決策も誰一人、指し示してはくれませんでした。
頼れる人も、心の支えとなる人もいない、十三年間の何もない人生だけが全て。
耐えても、耐えても、誰も助けてくれない現実。
助けを求めたくても、届かない、声。
私は責任の所在を明らかにしたいのではなく、
ただ、安心して心穏やかに生きたいだけだったのに。
それなのに「いじめられる方も悪い」という
喧嘩両成敗思想によって生いく手てを阻まれる命の重さは、
平等ではないと教えられた13歳の頃。
家庭では教えてくれないことを教えてくれるのが学校だというのなら、
皮肉な話ですが、
当時の同級生と担任教師は、
充分に学校としての責務を果たしたと言えるのかも知れません。

私が『三国志』と題された一冊の本と出会ったのは生死の狭間、
ギリギリを歩かされていた、まさに危急存亡の秋(とき)でした。
歴史は特に好きではなく、興味もそんなにない。
そんな私が、兄が買ってきたばかりの本を、
好奇心を抑えきれずについ、
手に取ってしまったのは、唯一の趣味が「読書」だったから。
内容は皆目見当もつかなかったけど、
本があったらとりあえず手に取ってみたい、
という衝動だけが私の命を『三国志』の前に運びました。
今思えば「何、これ?」
本の扉を捲った瞬間、私は千八百年の時空を超える扉を開けていたのかも知れません。

デジャブでも、前世の記憶でもない。
ましてや読書の醍醐味を満喫するように、
文字を読んで想像力を働かせたからでもありませんでした。
歴史や中国に何の興味も関心もない私が、
文字を追っただけで千八百年も昔の中国が
どんな風だったのか想像できるはずもないのだから。
が!確かに奇跡に似たその現象は起きたのです。
俄かに信じてもらえる話ではありませんが、
文字が文字ではなくなり、
目の前で三国志の世界が繰り広げられていく、そんな感覚でした。
今まで味わったことのない、土埃に塗れた日差しの匂い、
固唾を呑みこむ緊迫した音までもが、
生々しい感覚となって私の五感を支配した不思議なあの場景は
今でも鮮明に覚えています。

まるで私が「本」という名のタイムマシーンに乗って、
千八百年前の三国志の世界に足を踏み入れ、
彼らと喜怒哀楽をともにしているような、
そんな鼓動の高鳴りさえも物語の一部となって刻み込まれているような、
そんな時空間がそこにはありました。
今日に至るまで、もちろん『三国志』以外の作品も読んできましたが、
あの不思議な読書体験は人生で一度きり。
命を運んだところに運命が開ける、と言いますが
私の命と人生を救ってくれたのは、
神様でも仏様でもなく、三国志の英雄たちだったのです。

『三国志』は中国の戦乱の世を舞台とした歴史物語ですが、
私は三国志の英雄たちに人間としての温かさと、生きることの大切さ、
そして何よりも「やっと再会できた!」という喜びを強く感じていました。
誰ひとりとして助けてくれなかった生き地獄から、
私の人生と命を救うべく助け船を出してくれたのは、
一冊の本だけ。
これが仮にドラマや漫画、ゲームから入っていたら、
想像を超えた時空力が文字に宿ることはなく、
私の魂と共鳴することもなかっただろうと思うので同じ三国志でも、
その世界への入り方一つで人生が変わるんだなと思うと、、、
タイミングや縁って今生きている人間の専売特許じゃないんですね!
時空を超えた奇跡の縁は、十人十色。
自分に合った縁を大事にしてくださいね!
三度の飯より三国志世代の実態
クラスメートや担任からイジメを受けていた私が人間不信に陥ることなく、
生き地獄の日々に耐えて生きる道を選び、
人生の可能性と人の和を広げられたのは偏に三国志の英雄たちのおかげです。
イジメの辛さを忘れてしまうくらい、
私は三国志に夢中になったというのが一番大きいかも。
「感情が顔に出ないから何を考えているか分からない!
」とクラスメートに言われても
「それって玄徳殿と同じ、
喜怒哀楽の情を出さない系?何気に嬉しいかも〜」扱いで終了。
だったら、このままの自分でいいじゃん!
奴らに合わせる必要は全然ない!って思えました。
この時1991年。
まるで群雄が犇(ひしめ)くように所狭しと三国志関連の書籍が私の元に引き寄せられてきました。
さらに私と三国志の縁を応援するかのように「三度の飯より三国志」ブームが各地、、、かどうかは分からないけど、私が行く先々の書店で巻き起こっていました。
私の三国志の基盤となっている人形劇三国志やアニメ、
中国のドラマもほぼ同時期に出現しています。
特に、初の実写版三国志とも言える「諸葛孔明」と題された作品は衝撃的でした。
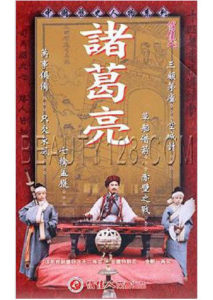
この作品です。李法曾さん主演。
当然のことながら、この作品を見た時、
私は三国志の英雄たちが話している中国語が全く聞き取れませんでした。
そりゃそうです。
それまで一度も、一言も中国語を学んだことはないのだから至極当然のことでした。
が!その当たり前すぎる現実は、どんなに大好きでも愛や情熱では超えられない障害があると教えてくれたのでした。
この時私は、言葉の壁は自力で超えなければならないのだと痛感するとともに
「今死んで仮に、孔明先生と会えたとしても中国語が解らないから話が出来ない!
その前に、私自身が人間として全然ダメダメだから三顧の礼どころか、
百万回謁見を求めても会ってもらえず、門前払いされるだけ!
イジメに負けて死んでいる場合じゃないわ!」
何がなんでも生きて、中国語を学んで、
孔明先生が会ってくださるような人間になることを
人生最大の目標として掲げることになったのです。
死して後已む、ではなく死んでからが始まりと言ったところでしょうか。

そう思うと、心も言葉も通じないクラスメートや
担任教師のイジメや存在はどうでも良くなりました。
彼らの嫌がらせに付き合っているほど私は暇じゃないし、
何よりも、広い地球でこの教室だけが全てじゃない。
地球上には日本以外にも中国という国がある。他の国もある。
今の環境が正解で死ぬまで永遠に続くわけじゃないんだと知ったら、
私の思考から自殺という選択肢は消滅していました。
2年にはクラス替えがあるから、まずはこの1年を生き抜こう。
生きる決断をした私を三国志の英雄たちが応援してくれるかのように、
私の三国志な人生は、私を苦しめた天地人に対して反撃を始めました。
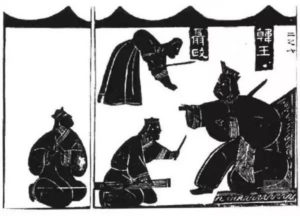
人生最悪の1年を終える少し前に父の仕事の都合で転校が決まったのです。
それまでも何度か転校をしており、
その都度、仲の良かった友達と分かれることを悲しんでいましたが、
この時だけは
「勝った!」と確信し思わずガッツポーズをしてしまいました。
イジメに勝った。死に勝った。人生に勝った。
1991年に三国志の英雄たちと再会していなければ私はもう、死んでいる、状態でした。
なので思います。
三国志と出会った年数が長ければ長いほどいいということはあり得ない。
その人にとって必要なタイミングで時空を超えた奇跡は起こります。
他人と比べて三国志との付き合いの長さを競うのではなく、
自分にとっての三国志な人生はどう成長しているのか?
どんなふうに三国志の英雄たちと生きているのか?
あくまでも三国志英雄と自分自身とのご縁を大事にして欲しいなと思います。
寡黙な玄徳公、現代人を黙らす
さて。何とか窮地を脱した私が転校したのは田舎町でした。
田舎町に転校生。
これほど無駄に人目を引くイベントもないだろう。
一難去ってまた一難。五関に六将を斬る関羽の千里行
、個別体験といったところでしょうか。

やっと平和な学生生活を送れるかと思いきや、
転校生という無条件に目立つ立ち位置を与えられた私は、
前年ほどではなかったが嫌がらせを受けた。
前年は老若男女問わず私に危害を加えたが、
転校先の2年目は男子生徒だけに限定された。
中学時代を通して男子クラスメートに
嫌な想いをさせられた結果、
未だに同い年の日本人男性は苦手。
いじめた方は忘れても、
いじめられた方は消えない
心の傷になっているので死ぬまで覚えているのです。
それでも、男性嫌いにならなかったのは、やはり三国志の英雄たちが居たからこそ。
友達が好きなアイドルの写真を切り抜いて
ファイルを作っていた頃、
私は三国志跡紀行が特集された雑誌を買って
お気に入りの写真を切り抜き、授業そっちのけで、
中国を旅している自分を想像しては、悦に浸った( ̄∀ ̄)
特に、いつの間にか、自然と人生の師として尊敬愛してい
た諸葛孔明先生が永眠する武侯墓の写真には、
何度も何度も心を熱くしながら頓首したものです。

そんな生活を送っていたので、
私の本棚と心には三国志以外、立ち入る場所はなし。
夏休みの宿題の定番である読書感想文は
「出師の表」を読んだ感想、というよりも
英雄たちへのラブレターのような手紙を書いて提出。
またある時は、校長が全校生徒に座右の銘を書かせたので玄徳公のお言葉を拝借。すると
「三国志を勉強しているんですか?」
校長が、一人ひとりの座右の銘を色紙に毛筆で書いてくれる特典付きだったが、
校長は私の座右の銘と、その説明を見るなり顔色を変えた。

「勉強というよりも好きなだけです」
勉強だったら三日と続かない。
「それは凄い。私なんて名前を覚えるのでも一苦労です」
当時、校長のいった言葉はよく分からなかったが、年を重ねると分からないでもない。
人の名前はよほど興味が沸かない限り、次の瞬間には読み方さえ忘れてしまうのだから。
「いやぁ、素晴らしい」
24時間、オンもオフもなく
三国志の英雄と生きている私にとっては、
極々普通のことだったが、
校長は大いに驚き感銘を受けたご様子。
そして何の前触れもなく突然、翌週の全校朝会で私の名前と
座右の銘を大々的に紹介するというとんでも行動に出たのだ!

こ、校長!!なんてことを!!!
目立たないよう、目立たないようにと息を殺すように生活をし、
何とか卒業まで一年を切っていた私に、諸行無常の響きあり。
全校生徒の前で私の宣伝をするとこの日の朝会は終わった。
私のためだけに全校生徒、全職員は体育館に集まったってこと!?
わ、訳わからん!死ぬぅう!きっといじめられる、、、。
そんな不安を大きくしながら教室へ戻るとー
突然、凄い人扱いをされたのだ。
クラスメートだけではなく学校中の先生に。
校長の、一国の主君の言葉とはこれほどまでに重いものだったのか!
と三国志的に解釈する癖はこの時から既に始まっていたらしい。
言うまでもなく、何だか知らないけど
凄い人になってしまった私への嫌がらせは
この朝礼を機にピタリと止んだ。
この時私は、玄徳公率いる三国志の英雄たちが守ってくれているんだと確信。
「いつか玄徳様にお礼を言いに行かないと、、、、」
そして、そんな心の声さえも玄徳公には届いていたのです。
玄徳公と武侯祠
その後、中国への修学旅行目当てで高校を受験し、
本場の中国へ行って三国志の国で暮らすことを決意した私は
高校卒業後、蜀の都である成都に留学しました。
もちろん成都に留学した理由はたった一つ!
三国志の聖都だから!!!
なのでいうまでもなく成都へ行って私が
最初に訪れた三国志跡は、成都にある武侯祠でした。

武侯祠とは諸葛忠武侯と呼ばれた孔明先生を祀る、
中国全土にある廟のこと。
成都武侯祠がある場所は元々は玄徳公の永眠地。
当時は帝位に就いたら、生前に墓を建てるのが通常だったので、
この聖地も玄徳公が皇帝に即位した後、
孔明先生が風水を駆使して厳選し、
全責任と尊重の念を込めてを着工したものでした。
それが今日の「昭烈陵」。

その後、後世の人たちが成都で主従再会をと願い
玄徳公の眠る昭烈陵の近くに蜀漢の英雄らとともに
孔明先生を祀る武侯祠を建立したと言われています。
それがいつの間にか、三国演義などの影響もあってか、
後世の人々が孔明先生のような
清廉にして高尚な政治家を望んでいたからか、
今日では武侯祠の方が有名になっており、
武侯祠の敷地内に昭烈陵があると思われがち。
ガイドブックを見ても
「成都武侯祠内にあるが目立たなくて忘れられることもある玄徳公のお墓」
と紹介されていたのです。
が! 実際に行ったら、何ということでしょう!!!

昭烈陵に眠る玄徳公を護るために建てられたのが武侯祠、という印象を受けました。
(あくまでも私個人の感想です)
昭烈陵には、武侯祠にはない孔明先生自身の想いも込められているからでしょうか?
玄徳公に会いに行くたび孔明先生にも会えているような、そんな気さえしたものです。
6年間の留学生活で100回以上訪れましたが、
そのどれもが私にとってはなくてはならない一期一会の時空を超えた謁見でした。

玄徳公と玄子(げんし)
慣れない異国での生活に戸惑ったり、
悩みを打ち明けたいことは多々ありましたが、
反対を押し切って留学していたので誰にも弱音を吐けませんでした。
そんな私が唯一、心の声を吐露できたのが玄徳公の墓前。
6年間の苦楽を一方的とは言え分かち合ってもらったことで、私にとって玄徳公は特別な存在になっていました。
そんなこんなで玄徳公に支えられながら留学生活に慣れた頃
孔明先生に少しでも近づきたくて、
孔明先生が好んで演奏していた中国の伝統楽器・古琴(七弦琴)を学んでいました。

三国志の時代は文化人の教養の一つとされていた古琴。
史書に態々記載する必要もないほど
文化人が古琴を嗜むことは常識レベルの楽器。
映画『レッドクリフ』で孔明先生と周瑜殿が共演した
楽器もこの古琴ですので覚えておいて損はなし。
巴蜀文化が色濃く残る成都で古琴の師匠に師事することが出来ただけで
も孔明先生に感謝!ですが、古琴が切っ掛けで、ひょんなことから兄弟子と知り合う縁がありました。
この日、成都にある「青羊宮」という道観で初めて彼らに出会いました。

三人の兄弟子に成都へ留学した理由を聞かれたので
「あの世で孔明先生に会いたくて、中国語と三国志文化を学ぶために成都へ来ました!」
私はいつものように奇怪っぷりを発揮。
普通は「変なの〜」「やばいんじゃない?』って反応をされますが、彼らは違いました!
「気に入った! 敬服いたした!」
彼らは、私を敬遠するどころか、拱手をして敬意を示したではありませんか。
それはきっと、
「我らが出家したのも、そのような熱い思いがあったればこそ」
彼らが俗人ではなく、時代を超えて道教文化に生きる道士だからなのかもしれません。

日本にいては袖擦り合う縁さえなかったであろう
三人の道士さんと知り合えただけでもこの上ない奇跡であり、
三国志への想いを理解してもらえただけでも
十分に驚きでしたが彼らはそんな私に
「中国名を授けたいが、良いかな?」
その場限りではない生涯の縁を授けてくれることになり
「成都で三国志といえば武侯祠だが、よく行かれるのかな?」
知り合った三人の道士さんのうち、
一番年長者の方が名付けの参考にすべく私の三国志愛を尋ねてくれたので
「毎週、玄徳公に会っています!
最も尊敬する孔明先生が人生と忠誠心を尽くした玄徳殿が
どんな人物なのか知りたくて通い詰めているうちに、惹かれてしまいました!」
いつもなら、惹かれるどころか、
どん引かれてすぐに話題を変えられてしまう本音だったが、
この人たちなら分かってくれるかもしれない!
と希望を見出すように熱弁すると
「それは素晴らしい! ならば、玄徳公から玄の字を頂こう
道教においても玄はとても大きな意味を持つから」
何とも恐れ多く光栄なことに、玄徳公を仲介役に私と道士さんたちの縁が、友情として結ばれたのでした。
そして、その名前は
「玄子!」
魂が感動で震えたのを今でも昨日のことのように鮮明に覚えています。

以来、私は好んで玄子という中国名を字として愛用するようになりました。
それはきっと、ソウルメイトならぬソウルネームだったから。
玄子という字を授かったことでやっと私の名前は完成し、
三国志な人生が本格的に始まったといっても過言ではありません。
宗教としての道教には全く知識も常識もなかったが、
それでもあの日から二十年近く経った今日でも
道士さん達との交流は続いているのは、
成都にいる玄徳公に会いにいくからこそ。
玄徳公との縁は私にとって、
人の和を大きく広げてくれる奇跡。
時代も国も違うけど、
命を救って活かしてくれる人たちと出会えた私は幸せだなって感謝でいっぱいです。
玄徳様へ
最後に。玄徳様へのお手紙を書きます。
玄徳様。
私に人間の優しさや温かさ、生きることの大切さと希望を教えてくれたのは玄徳様でした。
乱世でありながら、相手の心と命を大事にできる玄徳様に救われました。
命を削る極限状態に生きながらも相手を信じる大切さを身をもって教えてくれた玄徳様。
どんなに辛いことがあっても、耐え忍んで、耐え忍んで、でも、志と信念は無くさない。
今の平和な世の中でさえ難しい生き方をあの乱世で貫かれた真っ直ぐさにどれだけ救われたか、、、。
コロナ禍で人間力が問われる昨今。
心の乱世になろうとも、私は玄徳様のように相手を思いやる心を大事にしていける人間でありたいと思います。
私が中学生の時に座右の銘として、掲げた玄徳様の言葉は、年を重ねるごとに重さと深さを増しています。
玄徳様の祥月命日に当たる今日、その座右の銘をここに刻ませていただきます。
玄徳様との時空を超えた奇跡のご縁に感謝を込めて、、、。
玄子
勿以惡小而為之
勿以善小而不為